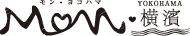私たちの街、国際都市横浜/フルールドリス代表 高橋としよさんにお話を伺いました
私たちの街、国際都市横浜
今回は、フルールドリス代表 高橋としよさんにお話を伺いました。高橋さんは現在アーティフィシャルフラワーによる戦略的空間プロデュースに取り組んでいらっしゃるフラワービジネスの専門家です。

高橋 としよ さん
これまでに、逗子市の米軍住宅敷地内で文化財保護の仕事を通した公私に渡る日米交流、国立大学の教授秘書として数々の学会や国際会議の準備から外国人研究者のアテンドまで、幅広く豊富な国際交流経験をお持ちです。
◆高橋さんにとって国際交流・国際化とは?
「違いを認める」「自分を知る」
わたしは留学などの経験はなく、おもに日本国内で諸外国の方々と出会い、日々の生活や仕事をとおして交流を深めてきました。
文科省の指針を見ると、「国際社会のグローバル化に乗り遅れないために」、「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画」などの文言が目につきます。
こどもに英語を習わせたい、習わせているという方も多いのではないかと思います。グローバルな人材ってどんな人だろう?と考えたとき、それは英語を話せるかどうかの問題ではないように感じます。話せないより話せる方が便利だけどね、という程度でしょう。
流暢な英語を話す深みのない人間と、英語は話さないけれど信念のある人間、どちらと仕事をしたいですか?
かれらも同じ人間ですから、英語を話す話さないにかかわらず、学ぶべきものを持っている人のことはちゃんと尊敬します。
グローバル化とは国や地域の境界を越えてヒトやモノ、経済や情報などあらゆるものが移動するということですが、最近では地産地消が推奨され、イギリスのEU離脱やトランプ大統領の国境の壁発言など、ローカル化への揺り戻しの感じもありますね。
日々変動する社会の中で、ほんとうの国際化とはどのようなことでしょうか。
それは、互いの違いを認め合うことだと思います。いろんな考え方の人がいていいよね、わたしは赤だけどあなたは白だと思うんだね、OKわかった、と受け入れられること。
逆説的ですが、相手の文化を受け入れるためにはまず自分の文化を知ることが大切だと思います。自国の文化を大切にできなければ他国の文化を敬うこともできないでしょう。
日本に来る外国人の多くは日本に興味があって、もっと知りたいと思って来ているのです。「あなたはこれをどう思う?」「それはなぜ?」「日本ではどうしてこうなの?」という、彼らの質問に答えられないのは英語力のせいだけでしょうか。
国際的な場面や交渉事などで日本人が弱いとされるのは、ものごとを理論的に考える訓練をしていない、自分の考えを言語化する習慣がない、間違えることを恥だと思う教育、などの方が大きいように思います。
◆日本人の美意識
「儚くて、不完全」
数年前に愛媛大学で開催された国際会議に参加する米国人研究者をアテンドした際、松山城をご案内すると、「日本でいうcastle(城)とはpalace(宮殿)のことなの?」と聞かれました。
かれの言うパレスがどういう意味で使われているのかわかりませんが、「領主として赴任してきた人が住むところで、ホワイトハウスのような感じ。戦のときは基地にもなる」というような説明をしました。
そして、前日現地入りで仕入れた一夜漬けの知識を披露します。
高橋:「これは江戸時代から残る数少ないオリジナルの天守なんですよ」
研究者:「ほかのものはどうしてなくなったの?」
高橋:「火事で燃えることも多かったようです。あとは明治の革命で壊されたり」
研究者:「じゃあヨーロッパの城のように石で造ればいいのに。日本人はどうして燃えやすい木と紙で造ったの?」
 こういう疑問は日本人はあまりもたないかもしれませんね、木造建物が当たり前だと思っていますから。
こういう疑問は日本人はあまりもたないかもしれませんね、木造建物が当たり前だと思っていますから。
高温多湿だから、地震があるから、木材が豊富だから、などが考えられますが、東南アジアにも石造遺跡はあるし、ヨーロッパも森林資源は豊富です。
ここはもう、「それが日本の美意識だからです」と言い切ります。べつにあちらも正解を知りたいわけではないでしょう。あとでネットで調べればいいわけですから。あなたはどう思うの?という会話や意見交換をしたいのです。
西洋人は「永遠」で「パーフェクト」が好きですよね。だから西洋文化は石と鉄、満月、満開の花、シンメトリー。でも日本人は「儚さ(fragile)」や「不完全」なものを美しいと感じるんです。だから木と紙、雲がかかった半月、散る花、アシンメトリー。
この説明は、気難しい科学者だとお聞ききしていたその方も、楽しんでくれたようでした。
◆世界の平和とは
「そこに知ってる人がいるから」
星の王子さまが、「だれかが、なん百万もの星のどれかに咲いている、たった1輪の花が好きだったら、そのひとは、そのたくさんの星をながめるだけで、しあわせになれるんだ」(内藤濯 訳)、と言っています。
わたしがアフリカのコミュニティビジネスに関心を持つようになったのも、はじめは、ただそこに知り合いがいたから。行ったこともないのに?と笑うひともいますが、それって十分な動機ではないでしょうか。
マラウイ人のミケカとは、かれが留学生として日本に住んでいたときに大学で知り合い、アフリカ東部にそんな小国があることをはじめて知りました。

かれの滞在中に東北の大震災があり、海外メディアは東日本は汚染されていると報道しました。多くの留学生が帰国したり、関西方面に避難したりする中、ミケカも報道を知ったお母さんから帰国するよう懇願されたけれど、「ぼくは科学者だよ。ぼくが横浜は安全だと判断したのに、お母さんはCNNの方を信じるの?」と説得したそうです。
地震を体験したことがなかったかれは、あのときパニックになって泣きながら外に飛び出してしまい、あとで研究室の仲間に恥ずかしかったと言っていました。日本人の冷静さはすごいと思った、と。ミケカは博士号取得後に帰国し、いまはマラウイ大学で工学を教えています。
どんな国にも、子を思う親がいて、友だちがいる。世界の平和とは、そうした個人レベルでの相互理解の積み重ねで実現してゆくものなのかもしれません。
◆花との出会い
「すべてはつながっている」
4年前のある日、ふとしたことでアーティフィシャルフラワー(造花)と出会い、その半年後にはフラワービジネスを起業していました。大学秘書の後任者への引継ぎが終わらず、兼任でのスタートでした。
それからずっと、これまでの経歴とは関係がない花の仕事を突然始めた意味を考えていましたが、最近「すべてが繋がっている」と感じています。

美術史や異文化を知っていること、多様な側面からものを考えられることは、わたしの大きな強みだと気がつきました。
ひとがなにかを美しいと感じる、心地よいと感じることのヒントは、いつも歴史や文化の中にあります。デザインとは、まったく新しいなにかを生み出すことではなく、長い年月をかけて培われてきたベースの上に自分なりのアレンジを加えていくことだと思います。
そして、今後は国際交流の経験をいかして、横浜エリアでのMICE事業の発展にフラワービジネスでかかわっていきたいと考えています。花による、お・も・て・な・しの心で、国際都市よこはまの魅力を世界に発信していかれるよう楽しく仕事に励みます!
アフリカ最貧国のひとつマラウイで、コミュニティビジネス立ち上げをめざす